まだ元気だから生命保険に加入しなくてもいいと考えていても、いきなり入院することになる人は珍しくないのです。しかし、生命保険に未加入な状態で入院することになってしまうと、非常に大きな負担となってしまうでしょう。生命保険に未 […]
まだ元気だから生命保険に加入しなくてもいいと考えていても、いきなり入院することになる人は珍しくないのです。
しかし、生命保険に未加入な状態で入院することになってしまうと、非常に大きな負担となってしまうでしょう。
生命保険に未加入で入院した場合はどうすればいいのか、解説します。
なぜ生命保険に加入しないのか
生命保険については、様々な場面で見ることもあり存在自体はほとんどの人が知っていると思いますが、加入していないという人も少なくないでしょう。
生命保険の未加入者の割合を年代別に見ると、男性は20代で53.6%、30代で18.5%、40代で13.9%となっています。
女性の未加入者は、20代で42.9%と男性よりも低いのですが、30代は17.2%、40代は13.7%と男女で大きな違いはなくなるのです。
なぜ生命保険に入らない人がいるのかというと、第一の理由として日本は保険制度があって公的医療保険に加入することが義務となっている、という点があります
病気になったときの治療費の負担が基本的に3割以下となるため、治療費が安くなっていれば生命保険は不要だと考える人も多いでしょう。
また、若い人が未加入である理由として特に多いのが、自分は病気になったりケガをしたりすることがないと考えているため加入しないという点があります。
若い人ほど自分が病気になることは想像できず、周囲にも病気になる同年代の人が少ないため、必要性を感じられないのでしょう。
3つ目の理由としては、何かあったとしてもどうにかできるだけの貯蓄があるから不要と考えています。
また、病気やケガの際は様々な公的保障を受けられる可能性があるため、保障の内容を知っているとますます生命保険を不要と考える可能性があるでしょう。
公的保障としてはまず高額療養費制度があり、1ヶ月の医療費が一定額を超えると超過分が健康保険から払われるという制度になっています。
年齢や所得で限度額は異なるのですが、差額ベッド代や病院での食事代などは対象外となるため注意が必要です。
2つ目の公的保障は傷病手当金といい、病気やケガが原因で働けなくなった場合に4日以上就業不可となると支給されます。
仕事を休んでいる間の給与支払いがないことも条件の1つであり、給与の3分の2が最長で1年半の間支給されるのです。
未加入のまま入院すると?
生命保険に未加入のまま入院することになっても、様々な公的保障などがあるのですが、何か困ることはあるのでしょうか?
まず、高額療養費制度で自己負担額の上限が決まっているとしても、対象外となる項目があるため必ずしも限度額までで収まるとは限りません。
例えば、病院に入院する際は鼓室しか開いていないため、強制的に差額ベッド代を支払うことになる可能性もあるのです。
鼓室などに入院することになった場合に発生する差額ベッド代は、1ヶ月入院した場合は19万円前後かかります。
また、先進医療は保険診療の対象外なので制度の限度額にも含まれないのですが、陽子線治療は約269万円かかるのです。
重粒子線治療はさらに高額で約319万円かかり、高周波切除器を用いて子宮腺筋膜症核出術の場合も約30万円かかります。
生命保険に加入する人の多くは怪我をしたときや病気になったときの不安に備えるために加入しているのですが、他にも長期入院の医療費が心配という人もいるのです。
また、もっと手厚い保障がないと安心できないという人や、差額ベッド代が心配という人も少なくありません。
入院することで仕事ができなくなるため、収入が減ってしまうことが不安という人も多いでしょう。
傷病手当金で3分の2は支払われるものの、元々の収入がギリギリという方は医療費もかさむ中で十分な収入とは言えないかもしれません。
生命保険の特約であったり単独の契約であったりするのですが、週病不能保険に加入していると収入の減少を補うことができるでしょう。
生命保険に加入していない人の中には、十分な収入がないため毎月の保険料という出費を抑えたいという人もいます。
しかし、保険金が負担となる人は十分な貯蓄がないことが多いため、いざ入院となったときには入院費用を支払うのが難しくなってしまうでしょう。
先進医療などの高額な治療方法を選ぶこともできず、収入の減少や途絶にも耐えられない可能性があります。
生命保険に加入していれば、小さな負担で大きな保障を得ることができるため、いざというときに備えて保障の小さな保険でもいいので備えておくべきです。
また、自営業の人は公的保険制度の傷病手当金を利用できないため、入院すると収入が完全に途絶えてしまいます。
生命保険に加入して就業不能特約を付けるか就業不能保険に加入しておくことで、収入を補うことができるのです。
専業主婦、あるいは主夫であれば、入院しても収入が途絶えたとはみなされないため傷病手当金が支給されることはありません。
しかし、実際には家のことをしてくれた人がいなくなればハウスキーパーやベビーシッターなどを雇う必要があるかもしれないのです。
当然、公的医療制度の対象には含まれないため自己負担となるのですが、生命保険に加入していればいざというときの助けになってくれます。
何より、自分に万が一のことがあったときに家族を守るため、死亡時に保険金が支払われる生命保険に加入することをおすすめします。
加入していなければ、葬儀代などは全て残された家族が負担することになってしまうため、せめて葬儀代くらいは残したいと思って加入する人も多いのです。
様々な理由で加入する人が多いため、本当にいざというときにそなえなくてもいいのか、もう一度よく考えてみてください。
最後に
生命保険は、20代などの若い世代ほど加入率が低く、30代でも10%以上が加入していなという状況です。
公的医療保険に加入していればいざというときには高額療養費制度や傷病手当金などがあるのですが、対象外となるものも多く十分な保障とはいえないかもしれません。
万が一への備えや入院に備えるだけの貯蓄がないという人、死亡時に家族を残していくという人は加入を検討した方が良いでしょう。
障害児通所支援とは
障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。
ご利用者のご状況や年齢により、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」および「居宅訪問型児童発達支援」などのサービスにわかれます。
また、サービスの利用に関する計画を相談・作成する「
障害児相談支援」があります。
支援を受けるにあたっては、「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。
障害児通所支援の種類について
児童発達支援
児童福祉法に基づくサービスの一つです。0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。
放課後等デイサービス
児童福祉法に基づくサービスの一つです。6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます
保育所等訪問支援
児童福祉法に基づくサービスの一つです。 保育所(保育園)、幼稚園や小学校等へ、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。
居宅訪問型児童発達支援
外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。
障害児相談支援
障害児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。
障害児通所支援を利用する場合には、原則として、障害児支援利用計画が必要です。
療育の内容
それぞれの施設(教室)により特徴を活かしているところがあります。学習・遊び・運動・言葉・社会との関わりなど、お子様の療育計画に沿って個別療育・集団療育(グループ療育)を実施しております。
ご利用料金について
児童福祉法に基づいた料金が発生します。利用料金のうち、世帯が負担する金額は1割です。また、その1割の金額には上限額が決められており世帯収入によって異なっております。
詳しくは、お住まいの市町村役場にお問合せまたは直接施設にご確認下さい。※市町村により特例を実施している場合もございます。
月々のご負担上限額(厚生労働省より)
| |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
| 生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
| 低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
| 一般1 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
| 入所施設利用の場合 |
9,300円 |
| 一般2 |
上記以外(世帯収入が概ね890万円以上の世帯) |
37,200円 |
2019年10月1日より就学前の障がい児の発達支援の
無償化されてます。
無償化の対象となるサービスについて
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
無償化の対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」になってます。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ないとのことですが、サービスを提供している事業所(教室など)や市区町村等へお問い合わせ頂ければと思います。
児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用するには!?
1.施設や教室の利用の目的
- 子どもの成長や発達の遅れが心配なので、将来自立して生活できるようにして欲しい。
- コミュニケーションが苦手なところを克服して欲しい。
- 学校以外での友達とも仲良くなれるようになって欲しい。
- 働いているので、夕方や夜まで預かって欲しい。
などなど、利用への目的があるかと思います。
2.施設の探し方や選び方のポイントは!?
それぞれの施設により、得意としていることや提供しているサービスなど異なっていますので、気になるポイントをピックアップして、各施設または相談支援施設等へお問い合わせすることから皆さん始まっています。
もちろん、送迎であったり平日以外もサービスを提供しているのか、運動プログラムやお外での体験が充実しているのかなどあるかと思いますが、気になる施設での体験教室や職員さんとのコミュニケーションを通して多くの場合選ばれております。
※ただ、お見合いみたいにいろいろ求めてしまうとなかなか決まらなかったりしますので、体験教室などで子どもさんが楽しくしていたとかで最終的には選ばれている方が多くなってます。
3.ご利用までの流れ
1.各施設へお問い合わせ
気になる教室や施設へお問い合わせすることから始まります。
2.ご相談
気になること、お悩みや教室のことなど、お子さまとご一緒だとよりいいかと思います。
3.体験教室
事業所や教室により、体験教室などを実施しています。
「うちの子にうまくやれるだろうか?」
「うまくやれるだろうか?」などなど、ご不安を解消するために大切なものです。
4.受給者申請・ご利用開始
市区町村へ通所受給者申請、ご利用の開始です。
まだ元気だから生命保険に加入しなくてもいいと考えていても、いきなり入院することになる人は珍しくないのです。しかし、生命保険に未加入な状態で入院することになってしまうと、非常に大きな負担となってしまうでしょう。生命保険に未 […]
当サイトで掲載している施設情報は、都道府県、市区町村等の行政機関等の公開情報やオープンデータや公示情報、各施設からの情報提供及び独自収集したものをより分かりやすく掲載しております。
しかしながら、本サイトに掲載されている施設情報およびコラム等の記事に関しては、月日の経過により古くなっていたり、修正されている場合や公開時より間違ってしまっている場合(公開情報やオープンデータ含め)があり、その内容の完全性、正確性、有用性、安全性等については、いかなる保証を行うものでもありません。掲載情報に基づいて利用者が下した判断および起こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、当サイトはその責を負いませんので予めご了承ください。ご自身のご判断のもとほんの参考程度にして頂きまして、必ず直接各施設や行政機関に確認及びお問い合わせ頂きますようお願い致します。
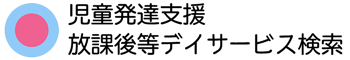
※上記は、一つの例になります。幼稚園や保育園のような事業所もあれば、お昼頃まで支援しているところや朝から夕方まで預かっているところなどそれぞれです。また、事業所によっては送迎をしているところもあります。