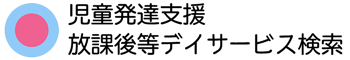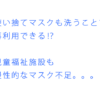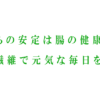太陽光発電は、自宅や自社で電力を使用するだけではなく、余った電力を売却する売電という制度があったことで広く普及してきたのです。
売電制度で重要なのが、国が買取価格を決める固定価格買い取り制度(FIT)ですが、2032年に制度が終了してしまうのです。
太陽光発電に起こる2032年問題について、解説します。
太陽光発電2032年問題とは?
太陽光発電は、今や一般家庭でも設置している住宅が増え、広大な土地にソーラーパネルを並べている事業者も多いでしょう。
太陽光発電で余った電気は、余剰電力買取制度によって電力会社に買い取ってもらうことができるため、普及も一気に広まりました。
売電制度が始まったのは2009年で、2012年からはFIT制度が開始して固定価格で買い取ってもらえるようになったのです。
しかし、FIT制度が有効なのは売電を始めてから10年間と定められていたため、2019年には買取価格が下がってしまう人が多く出ていました。
2019年問題といわれていたのですが、今回は2032年問題となって今から7年後の2032年に、2019年問題と同じような問題が生じることとなったのです。
2019年問題は、出力10kW未満の太陽光発電を設置していることが多い、個人での発電が対象となりました。
しかし、事業者によくみられる出力10kW以上の産業用太陽光発電の買取は2012年からスタートしていて、買取が可能な期間は20年間となっています。
つまり、2032年になるとFIT制度の対象外となってしまう事業者が多いため、問題となるのです。
FITがすでに満了している家庭では、電力の買取価格がかなり下がっているため、売電に向けた意欲も下がってしまいます。
初期の買取価格は40円以上だったのですが、FITが終了してしまうと10円未満での買取になってしまうのです。
設置する際の宣伝文句は、売電終了を家計の足しにとなっていたのですが、FITが終了することで収入は4分の1以下になってしまいます。
近年では、電気代の高騰に伴って余剰の電力を売却するのではなく、蓄電池を導入して自家消費するケースも増えているでしょう。
昼間に発電して夜間に使用することで、高い電力を使用する必要がなくなり売電価格の低下による損失を補うことができます。
2032年問題の場合は、産業用太陽光発電の電力買取価格が低下し、固定価格で売却できなくなるのです。
産業用の場合は、全量を売電することが多いため、売却して売電収入を得ることが目的となっています。
各企業で発電所を経営しているようなものですが、買取価格が下がってしまうと採算性は大幅に低下してしまうのです。
収支をシミュレーションする際はFIT制度が有効な間を基準としていることも多いため、20年が経過したら売却や閉鎖も考えているかもしれません。
FITが終了しても、規模が大きければ発電所を集約して特定の事業者に売電することもできますが、最も影響を受けるのは小規模な太陽光発電事業者です。
小規模だとスケールメリットを生かすことができず、集約して特定の事業者に売電することができないため、事業から撤退することになるかもしれません。
しかし、事業から撤退した際はソーラーパネルが不要となるため、パネルや周辺の機材など大量の廃棄物が発生してしまうでしょう。
そもそもソーラーパネルは20~30年で寿命になるといわれているため、寿命を迎えるタイミングで事業から撤退しようと考える投資家も多いと思われます。
小規模事業者というのは、出力が50kW未満の事業者のことをいい、空き地や休耕地、山の斜面の一部に設置しているケースがあてはまるでしょう。
小規模な事業者は、FITのために事業を開始していることも多いため、FITが終わってしまえば用済みになってしまいます。
しかし、ソーラーパネルが大量に廃棄されることとなれば、エコなエネルギーのはずなのに環境へと与える負荷が大きくなってしまうのです。
産業用太陽光発電の9割以上は小規模事業者となるため、事業者の動きが大きな影響を生み出すこととなります。
2032年問題は国も認識していて、小規模事業者を集約したり大規模化を促進したりすることで乗り切ろうと考えているのです。
FITの終了に備えた対策は?
FITは順次終了していくことが決まっている制度なので、FITが続くことを望むのではなく今まで恵まれていただけだと考えましょう。
国は、再生可能エネルギーである太陽光発電を促進するために始めた制度なので、ある程度普及したと判断されれば制度を継続する必要性はないのです。
しかし、FITが終了しても太陽光発電ができなくなってしまうということはなく、近年ではパネルの寿命を長くする技術も進歩しています。
FITが終わっても発電ができる以上、2032年以降に生み出される電力の有効活用について考えることが重要となるでしょう。
FIT終了後の活用方法の1つが自家消費ですが、中古太陽光発電所の売買という選択肢もあります。
また、さらに重要となるのがFITに依存しない太陽光発電所の電力であり、Non-FIT電源とも呼ばれるものです。
近年は、ビジネスにおいても環境意識が高まっていて、企業が使用している電力も節電だけではなく、電力の質にも注目されています。
欧米では、火力発電所のような環境負荷の高い電力を使用している企業には投資をしない、エシカル投資という考えも浸透しています。
今や、企業は環境への影響を無視した経営を続けていると、投資不適格とみなされてしまうリスクがあるのです。
日本の企業も例外ではなく、ESGやSDGsなども広まっていることから、環境品質が高い電力のニーズが高くなっています。
Non-FIT電源であれば、太陽光発電によって得られた電力を安定供給することができ、企業はRE100などの第三者認証を得ることで環境品質が高い企業になるのです。
FITに依存しない発電所を経営したい事業者と、環境品質が高い電力を求める企業とをつなぐことで、2032年問題の解決にもつながっていきます。
まとめ
2019年問題という、個人の住宅に設置された太陽光発電の多くの売却価格が固定価格ではなくなるという問題があったのですが、2032年にも同様の問題が起こるのです。
産業用太陽光発電の固定価格制度が2032年から順次終了となるため、小規模事業者を中心として太陽光発電から撤退してしまう可能性があります。
太陽光発電は企業の環境意識の高まりによって需要も高くなっているため、Non-FIT電源に変化させて続けるようにしましょう。